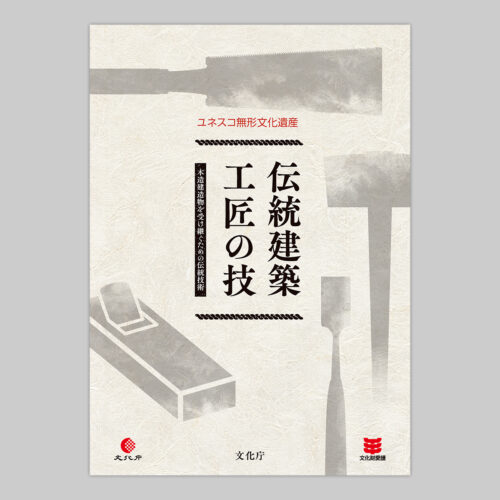日本の伝統建築の保存修理に欠かせない伝統技術。その技術が「伝統建築工匠の技:木造建造物を受け継ぐための伝統技術」として、2020年12月にユネスコ無形文化遺産に登録されました。登録を記念して、国が文化財保護制度により選定した17の「選定保存技術」のうち当館企画展に関連した技術に着目し、当館1F多目的ホールにて連続講演会を行います。 |
|
| ユネスコ無形文化遺産とは | これまで世界遺産条約が対象としてきた有形の文化遺産に加え、無形文化遺産の保護を目的として2003年に採択された条約。口承による伝統及び表現、芸能、社会的慣習、伝統工芸技術などの無形文化遺産を対象としており、締約国が自国内で目録を作成し保護措置をとることや、国際的な保護をするのに必要な一覧表の作成、国際的な援助などが定められている。 *文化庁HPより |
|---|---|
| 「伝統建築工匠の技」とは | 木・草・土などの自然素材を建築空間に生かす知恵、周期的な保存修理を見据えた材料の採取や再利用、健全な建築当初の部材とやむを得ず取り替える部材との調和や一体化を実現する高度な木工・屋根葺(ぶき)・左官・装飾・畳など、建築遺産とともに古代から途絶えることなく伝統を受け継ぎながら,工夫を重ねて発展してきた伝統的木造建築技術。 ■公式ウェブサイトはこちら➡︎ |
| シリーズ一覧 | 【1】「建造物漆塗けんぞうぶつうるしぬり」✖ 匠 *開催終了 東照宮の建造物は建物の格式によって漆塗りの色が異なります。創建当時の塗装痕・彩色痕の事例を通して、江戸時代から令和まで守り伝えられてきた漆塗り・彩色の技法、材料などについて紹介します。
|
| 【2】「建具製作たてぐせいさく」✖ 匠 *開催終了 数百年経ってもなお、機能し続ける建具。修理の現場でしか知り得ない、伝統建具に隠された秘密とは。長年文化財建造物の修復に携わってこられた専門家と職人のお二方をお招きし、伝統建具に秘められた魅力について語り合います。
|
|
| 【3】「縁付金箔製造えんつけきんぱくせいぞう」✖ 匠 金沢で生産されている縁付金箔は、国宝や重要文化財の修復に必ずといってよいほど用いられています。伝統的な技法により時間と手間をかけて作られ、その製造の特筆すべき点として手漉き和紙を使用することが挙げられます。この伝統的な工程と、金箔の今と昔についてお話します。
|
|
【4】「檜皮採取ひわださいしゅ」✖ 匠
|
|
【5】「茅葺かやぶき」✖ 匠
|
|
| ※内容は予告なく変更になる場合があります。詳細は決まり次第、順次公開予定です。 |